【絵画史上、最大のナゾ】浮世絵師「写楽」とは、いったい何者だったのか? 1年で大量の作品を生み、姿を消した天才
日本史あやしい話43
■写楽とは、いったい誰のことなのか?
文人・大田南畝が著した『浮世絵類考』に月岑が加筆した書(『増補浮世絵考』)に記したものによれば、「写楽が能役者・斎藤十郎兵衞であった」という。
後々に判明したことをまとめてみれば、この斎藤十郎兵衞なる御仁、実は阿波徳島藩藩主蜂須賀家お抱えの能役者で、生年は宝暦11〜13(1761〜1763)年頃で、江戸八丁堀にあった阿波藩藩邸に居住。
ワキ(主人公であるシテの脇役)の万作の弟子で、本人はワキツレ(ワキの同伴者)として活動していたようである。その能役者が、1年間の非番を利用して絵の制作に励んだという。以降、「写楽は斎藤十郎兵衞だった」というのが、半ば定説のように思われながら今日に至るのである。
しかし、それって、本当のことなのだろうか? 実のところ、この説に疑問を投げかける識者も少なくない。
その理由の一つが、わずか1年にも満たない内に、本当に145点余もの人物像を一人で描くことができたのか?という素朴な疑問である。また、発刊する時期によって絵の特徴が大きく変わっていった点や、落款が「東洲斎写楽」と「写楽画」の2種類あったというのも謎。
そこに何か秘密が隠されていると見るのが『六人いた!写楽』(宝島社新書)を著した橋本直樹氏であった。同書に「写楽が誰であったのか」について、実に興味深い意見が述べられているので、参考にさせていただくことにしたい。
■「写楽は6人いた!」との興味深い説
同氏によれば、本のタイトルにもあるように、写楽は6人いたという。端的にいえば、大首絵を描いたのを斎藤十郎兵衞の可能性があるとしながらも、歌麿の女弟子・千代丸の関与をも示唆。
さらに栄松斎長喜や山東京伝、十返舎一九ばかりか、出版プロデューサーであった蔦屋重三郎本人までもが、後続の作品制作に関わっていたと推察するのである。作品ごとに誰がどのような意図で描いたのかについても記しているので、是非一読していただきたい。
なお、写楽のひとりと見なされる斎藤十郎兵衞であるが、平成9(1997)年に埼玉県越谷市の今日山法光寺において、斎藤十郎兵衛の名を記した過去帳が発見されたことで、その実在が証明されている。
没年は、文政3(1820)年で、58歳だった。また、発刊に携わった蔦屋重三郎は、写楽を世に出した3年後の寛政9(1797)年、脚気を患って48歳でこの世を去ったとも。
ともあれ、冒頭で紹介したように、大河ドラマの主人公は蔦屋重三郎であるが、東洲斎写楽も当然のことながら大きくクローズアップされることは間違いないだろう。どうやら2025年は、写楽ブーム再来となりそうである。
- 1
- 2

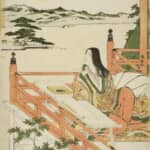


-e1704957789649-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
